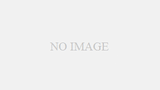1. はじめに
1.1 背景と目的
Oracle WebLogic Server は、エンタープライズ Java アプリケーションの実行基盤として広く利用されているアプリケーションサーバーです。
最新バージョンである 14.1.2.0.0 では、Jakarta EE 8 準拠の維持に加えて、Oracle JDK 21(例:21.0.4) の正式サポートや最新のセキュリティ標準への対応が強化されています。
また、クラウドやコンテナ環境を見据えた運用性の改善も含まれており、オンプレミスにとどまらずハイブリッド IT 環境にも柔軟に対応可能です。
従来の Web ブラウザベースの管理コンソール(/console)は WebLogic Server 14.1.2 以降では廃止されており、GUI による管理は WebLogic Remote Console(WRC) に統一されています。
そのため、構築直後の動作確認やドメイン管理などは、WRC を活用する構成を前提としています。
本記事では、AlmaLinux 9.6 上に Oracle WebLogic Server 14.1.2.0.0 を構築する手順を解説します。
AlmaLinux は Red Hat Enterprise Linux(RHEL)互換のコミュニティ主導ディストリビューションであり、公式にサポートされる OS は Oracle Linux / RHEL / SLES など 認定マトリクスに掲載されたものに限られます。
したがって AlmaLinux は Oracle による公式サポート対象ではありませんが、RHEL 相当の挙動を持ち、商用サブスクリプションを必要としないため、学習や検証用途の構築に適した環境といえます。
本記事で扱う構築環境は以下のとおりです。
- OS: AlmaLinux 9.6(最小構成、GUI なし)
- Java: Oracle JDK 21.0.4
- アプリケーションサーバー: Oracle WebLogic Server 14.1.2.0.0
- データベース: Oracle Database 23ai(別サーバーに構築済み)
本記事の目的は、最新の WebLogic 環境を誰でも再現可能な形で構築できる標準手順を提供し、学習や検証、実務への応用を支援することです。
具体的には次の観点を重視します。
- 実行可能なコマンド例の提示と解説
- 構築後に確認すべき動作チェックポイントの明示
- セキュリティや運用管理に配慮した設定の紹介
これにより読者は、自身の環境で WebLogic Server を構築・検証し、安定したアプリケーション基盤を確立できるようになります。
本構成は「単一構成(AdminServer のみ。アプリケーションは未配置)」の最小環境を前提としていますが、
将来的に Managed Server を追加し、本番同等の構成に拡張することも容易です。
1.2 前提条件と構成概要
本記事では、Oracle WebLogic Server 14.1.2.0.0 を AlmaLinux 9.6 上に構築するにあたり、必要となる前提条件とシステム構成の概要を説明します。
この節は、後続の構築作業を円滑に進めるための土台となる情報を提供するものです。
前提条件
- OS: AlmaLinux 9.6(最小インストール、GUI なし)
※RHEL 互換ディストリビューションですが、Oracle による公式サポート対象は Oracle Linux / RHEL / SLES など 認定マトリクスに掲載された OS に限られます。AlmaLinux は検証・学習目的の例として利用しています。 - Java: Oracle JDK 21.0.4(LTS 対応)
- DB: Oracle Database 23ai(別サーバーで構築済み)
- ユーザー: WebLogic 用の専用ユーザー(例:
oracle)を作成済み - パッケージ: 必須パッケージ(glibc, libaio, unzip, tar, which 等)が導入済み
- ネットワーク: ポート
7001が外部からアクセス可能であること - SELinux: 無効化済み(後続手順にて実施)
構成概要
本構成は、以下のようなシンプルな単一構成を前提としています。
| 構成要素 | 内容 |
|---|---|
| OS | AlmaLinux 9.6(最小構成) |
| Java | Oracle JDK 21.0.4(/usr/java/jdk-21 にリンク) |
| WebLogic バージョン | 14.1.2.0.0 |
| ドメイン構成 | 単一構成(AdminServer のみ。アプリケーションは未配置) |
| モード | Production モード |
| JVM 設定 | ヒープサイズ:-Xms1024m -Xmx1024mGC: -XX:+UseG1GC |
| ドメイン名 | base_domain |
| データベース | Oracle Database 23ai(別サーバー) |
今後の手順との関連
この構成に基づき、次章以降では OS の初期設定から WebLogic のインストール、ドメイン作成、JDBC 接続、Remote Console の導入、
最終的な起動・検証までの一連の手順を順に解説します。
なお、本構成は学習・検証目的に最適化されており、
高可用性やスケーラビリティを重視した本番構成とは異なります。
Managed Server の追加やクラスタ構成など、より実践的な拡張は別途解説予定です。
2. OS 初期設定
2.1 Firewall の無効化
Oracle WebLogic Server を構築する際、Linux のファイアウォール設定(firewalld や iptables)が有効のままだと、
WebLogic の管理ポート(デフォルト:7001)へのアクセスがブロックされる可能性があります。
本節では、検証・学習目的での環境構築を前提として、firewalld を無効化するシンプルな手順を紹介します。
なお、本番環境では firewalld を有効のまま必要なポート(例:7001)を開放し、セキュリティポリシーに沿って運用することを推奨します。
■ firewalld の無効化手順(AlmaLinux 9.6)
実行ユーザー: root
# firewalld を即時停止し、次回以降も無効化
systemctl disable --now firewalld
# 状態確認(inactive が表示されれば OK)
systemctl is-active firewalld
■ (本番向け)firewalld を有効のままポート開放する例
本番環境や共有環境では firewalld を維持しつつ、必要なポート(7001)のみを開放してください。
# 管理ポート 7001 を TCP で開放
firewall-cmd --permanent --add-port=7001/tcp
# 設定を反映
firewall-cmd --reload
# 開放されていることを確認
firewall-cmd --list-ports
■ iptables / nftables 確認(補足)
AlmaLinux 9 では firewalld の内部に nftables が使われていますが、
環境によっては iptables サービスが稼働している場合もあります。
必要に応じて以下のコマンドで確認してください。
# iptables サービスのステータス確認(稼働している場合のみ対応)
systemctl status iptables
■ 注意事項
- この設定は WebLogic Server を構築する前に実施してください。
- この時点では WebLogic Server は未インストールのため、ポート 7001 の通信確認は不要です。
- 本番運用では firewalld を無効化せず、必要最小限のポート開放で運用することが望まれます。
2.2 SELinux の無効化
Oracle WebLogic Server を AlmaLinux 9.6 上に構築するにあたり、SELinux(Security-Enhanced Linux) の設定は重要な初期作業のひとつです。
SELinux が有効な状態では、WebLogic Server のファイルアクセスやポート通信が制限され、構築中に予期せぬエラーが発生する場合があります。
検証・学習環境においては SELinux を無効化するのが一般的です。
一方で、本番環境では「Permissive モード」での動作確認 → ポリシー調整 → Enforcing モードへの移行が推奨されます。
■ 一時的な無効化(実行ユーザー:root)
# SELinux を一時的に無効化(再起動で元に戻る)
setenforce 0
■ 永続的な無効化(実行ユーザー:root)
# /etc/selinux/config を直接編集して disabled に設定
sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config
変更を反映するには再起動が必要です。
reboot
■ 状態確認(実行ユーザー:root)
getenforce
出力が Disabled であれば完全に無効、Permissive であればログ記録のみ許可状態です。
■ 本番環境での扱い
- セキュリティ要件が厳しい環境では、Permissive モードでの検証後、必要なポリシーを設定して Enforcing モードに移行してください。
- 例えば、WebLogic Server の 7001 ポートを SELinux に許可するには以下のように設定します:
semanage port -a -t http_port_t -p tcp 7001
このコマンドにより、SELinux が 7001 ポートでの通信を許可するようになります。
■ 注意事項
- SELinux を完全に無効化すると、カーネルによるアクセス制御が適用されなくなります。
- 本記事の手順は閉域環境や検証環境を前提としています。本番では Permissive/Enforcing での運用を推奨します。
2.3 必要パッケージの導入
Oracle WebLogic Server 14.1.2.0.0 を AlmaLinux 9.6 上に正しくインストール・実行するには、事前にいくつかのシステムパッケージを導入しておく必要があります。
これにより、JDK の展開や WebLogic インストーラ実行時に発生し得る依存関係エラーを防ぐことができます。
■ 実行ユーザー
root ユーザーで実行します。
■ 基本パッケージ(最低限必要)
glibc:C ランタイムライブラリ(通常は標準で導入済み)。libaio:非同期 I/O を使う一部の Oracle 製品で必要。unzip,tar,gzip:アーカイブファイルの解凍に使用。which:コマンドのパス確認やスクリプト実行時に使用。
■ 追加パッケージ(必要に応じて)
compat-openssl11:OpenSSL 1.1 互換ライブラリ。
古い JDBC ドライバや外部ライブラリが OpenSSL 1.1 に依存する場合のみ必要です。
Oracle WebLogic Server 本体は Java の JSSE を利用するため、通常は不要です。
■ インストールコマンド
# 必要な基本パッケージをまとめて導入
dnf install -y libaio unzip tar gzip which
# glibc が未導入の場合のみ(通常は不要)
dnf install -y glibc
# 特定の構成で必要な場合のみ
dnf install -y compat-openssl11
■ 補足:OpenSSL のバージョン互換性
AlmaLinux 9.6 では標準で OpenSSL 3.x が導入されています。
旧バージョンの JDBC ドライバや外部ライブラリの中には OpenSSL 1.1 に依存しているものがあるため、
そういった場合にのみ compat-openssl11 パッケージを追加してください。
Oracle WebLogic Server 14.1.2.0.0 では通常は Java が提供する JSSE(Java Secure Socket Extension) を通じて TLS 通信を行うため、
compat-openssl11 を必須とするケースはまれです。
2.4 WebLogic 用ユーザーとディレクトリの作成
WebLogic Server を安全かつ一貫性のある方法で運用するためには、専用の OS ユーザーとディレクトリ構成を整備することが重要です。
本節では、oracle ユーザーの作成と、WebLogic Server のインストールや運用に必要なディレクトリ群の準備を行います。
2.4.1 oracle ユーザーとグループの作成
WebLogic Server は Oracle 製品の一部として構成されるため、インベントリ管理用のグループ(oinstall)を用いるのが一般的です。
まずはこのグループとユーザーを作成します。
# グループ作成(必要に応じて)
groupadd oinstall
# oracle ユーザー作成(ホームディレクトリ付き)
useradd -g oinstall -d /home/oracle -m -s /bin/bash oracle
# パスワード設定(仮パスワードは Welcome1 等を指定)
passwd oracle
上記により、グループ oinstall に所属するユーザー oracle が作成され、
ホームディレクトリ /home/oracle も自動で生成されます。
補足:
Oracle Inventory 用に作成する /etc/oraInst.loc では、グループとして oinstall を指定します(後述)。
2.4.2 必要ディレクトリの作成と権限設定
WebLogic の各種ファイルを保存するために、以下のディレクトリを作成します。
これらは /u01 配下に配置するのが一般的です。
/u01/oracle/middleware– WebLogic Server のインストール先(ORACLE_HOME)/u01/oracle/domains– ドメイン(構成ファイル群)の格納先/u01/oracle/logs– 各種ログファイル保存先
実行ユーザー: root
# ディレクトリ作成
mkdir -p /u01/oracle/{middleware,domains,logs}
# 所有者・グループを oracle:oinstall に変更
chown -R oracle:oinstall /u01
# アクセス権を設定
chmod -R 755 /u01
これにより、oracle ユーザーがこれらのディレクトリにアクセス・操作できるようになります。
2.4.3 作成内容の確認
以下のコマンドで、ユーザーとディレクトリの作成状況を確認します。
# oracle ユーザーの確認
id oracle
# 出力例:
# uid=1000(oracle) gid=1000(oinstall) groups=1000(oinstall)
# ディレクトリと権限の確認
ls -ld /u01/oracle/*
# 出力例:
# drwxr-xr-x 2 oracle oinstall 4096 ... middleware
# drwxr-xr-x 2 oracle oinstall 4096 ... domains
# drwxr-xr-x 2 oracle oinstall 4096 ... logs
これで WebLogic Server のインストールに向けた準備が整いました。
次節では JDK のインストールと環境変数の設定に進みます。
3. JDK 21 のインストール
3.1 JDK の展開と環境変数設定
Oracle WebLogic Server 14.1.2.0.0 を AlmaLinux 9.6 上で動作させるためには、対応する Oracle JDK 21 を事前にインストールしておく必要があります。
ここでは、JDK 21.0.4 を例に、JDK アーカイブの展開と環境変数設定の手順を解説します。
■ 手順概要
- Oracle JDK 21.0.4 のアーカイブを取得
/usr/javaに展開(バージョン付きディレクトリ)/usr/java/jdk-21という名前でシンボリックリンクを作成/etc/profile.d/jdk21.shを作成して環境変数を設定
■ 作業ユーザー
root ユーザーで実行
■ JDK のダウンロードと配置
Oracle 公式サイトより、Linux x64 用の JDK 21.0.4 アーカイブ(.tar.gz)をダウンロードします。
事前に Windows PC などから取得し、Linux サーバへ転送してください。
ファイル転送の例:
scp jdk-21.0.4_linux-x64_bin.tar.gz root@<ホスト名>:/root/■ JDK の展開とリンク作成
# 展開先ディレクトリを作成
mkdir -p /usr/java
# JDK を展開
tar -xvzf /root/jdk-21.0.4_linux-x64_bin.tar.gz -C /usr/java
# シンボリックリンク作成(保守性向上のため)
ln -sfn /usr/java/jdk-21.0.4 /usr/java/jdk-21
このようにして、JDK の実バージョンを切り替えても /usr/java/jdk-21 を変更するだけで済む構成になります。
■ システム環境変数の設定
JAVA_HOME と PATH をシステム全体に反映させるため、以下のファイルを作成します。
vi /etc/profile.d/jdk21.shファイル内容:
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk-21
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
実行権限を付与:
chmod +x /etc/profile.d/jdk21.sh
■ 設定の反映(再ログインまたは source)
source /etc/profile.d/jdk21.sh
■ 補足
- 複数の JDK バージョンを使う場合は
alternativesコマンドで切り替える方法もあります。 - ここでは簡潔な管理のため、
/usr/java/jdk-21を固定の参照先として構成しています。 - systemd で WebLogic を自動起動する場合、
/etc/profile.dの設定は読み込まれないため、ユニットファイル内でJAVA_HOME=/usr/java/jdk-21を明示する必要があります(10.1 節参照)。
3.2 インストール確認
前節にて、Oracle JDK 21.0.4 を /usr/java/jdk-21 に展開し、
環境変数 JAVA_HOME および PATH を設定しました。
本節では、その設定が正しく反映されているかを確認します。
■ 実行ユーザー
root または oracle ユーザー
(/etc/profile.d/jdk21.sh により、全ユーザー共通で JAVA_HOME が設定されているため)
■ java コマンドのバージョン確認
$ java -version■ 期待される出力例
java version "21.0.4" 2024-07-16 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 21.0.4+9-LTS-123)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.4+9-LTS-123, mixed mode)
出力結果において、「java version」の値が 21.0.4 であり、
さらに Java(TM) の表記が含まれていれば Oracle JDK が利用されていることを確認できます。
■ JAVA_HOME の確認
$ echo $JAVA_HOME/usr/java/jdk-21
JAVA_HOME が正しく設定されていることを確認します。
■ java コマンドのパス確認(任意)
$ which java/usr/java/jdk-21/bin/java
which の結果が JAVA_HOME/bin/java を指していれば、
環境変数 PATH の設定も正しく反映されています。
以上により、Oracle JDK 21.0.4 が正しくインストールされ、環境変数も有効であることを確認できます。
4. WebLogic Server のサイレントインストール
4.1 Oracle Inventory の準備
Oracle WebLogic Server をサイレントインストールする前に、Oracle Inventory を準備する必要があります。
これは Oracle 製品のインストール情報を一元管理するための仕組みで、Oracle Universal Installer(OUI)が利用します。
■ Oracle Inventory とは?
Oracle Inventory は、Oracle 製品のインストール先・バージョン・パッチ履歴などを記録するリポジトリです。
サイレントインストールを行う際にも、この情報が必要となります。
■ 構成方針と前提
- Oracle Inventory は
/u01/oracle/oraInventoryに作成 - 所有者は
oracleユーザー、グループはoinstall /etc/oraInst.locに Inventory の位置とグループを登録
1. Oracle Inventory ディレクトリの作成
実行ユーザー: root
mkdir -p /u01/oracle/oraInventory
chown -R oracle:oinstall /u01/oracle/oraInventory
chmod -R 775 /u01/oracle/oraInventory
2. oraInst.loc ファイルの作成
実行ユーザー: root
cat <<EOF > /etc/oraInst.loc
inventory_loc=/u01/oracle/oraInventory
inst_group=oinstall
EOF
chmod 664 /etc/oraInst.loc
3. 作成内容の確認
cat /etc/oraInst.loc
# 出力例:
# inventory_loc=/u01/oracle/oraInventory
# inst_group=oinstall
4.2 レスポンスファイルの作成
WebLogic Server のサイレントインストールを実施するには、事前にレスポンスファイル(response file)を用意する必要があります。
このファイルには、インストール先ディレクトリやインストールタイプなどの情報を記述し、対話なしでの自動インストールを可能にします。
■ レスポンスファイルとは
レスポンスファイルは、Oracle インストーラが必要とする入力項目を事前に定義した設定ファイルです。
これを用いることで、GUI を使用せずに完全な無人インストールを実現できます。
■ 作成ファイルとパス
- ファイル名:
wls_silent.rsp - 保存場所:
/u01/software/(インストール作業用ディレクトリ) - 作成ユーザー:oracle
■ 作成手順
# oracle ユーザーで作成
mkdir -p /u01/software
vi /u01/software/wls_silent.rsp
■ レスポンスファイルの例(最小構成)
[ENGINE]
Response File Version=1.0.0.0.0
[GENERIC]
ORACLE_HOME=/u01/oracle/middleware
INSTALL_TYPE=WebLogic Server
DECLINE_AUTO_UPDATES=true
■ 各項目の説明
ORACLE_HOME:WebLogic Server をインストールするルートディレクトリ(例:/u01/oracle/middleware)INSTALL_TYPE:インストールタイプ(通常はWebLogic Serverを指定)DECLINE_AUTO_UPDATES:自動更新を無効化(サイレントインストールでは必須指定が推奨)
■ ファイルの保護
レスポンスファイルには認証情報は含まれませんが、不要な変更や誤使用を防ぐため、権限を制限しておきましょう。
chmod 600 /u01/software/wls_silent.rsp
■ 確認事項
ORACLE_HOMEのパスが正しいこと(実際に存在するディレクトリ配下)INSTALL_TYPEが正確に指定されていることDECLINE_AUTO_UPDATESを設定していること- レスポンスファイルの保存場所がインストーラ実行ユーザー(oracle)から読み取り可能であること
■ 参考情報
レスポンスファイルの詳細項目はバージョンや構成によって異なる場合があります。
最新の公式サンプルファイルはインストーラ ZIP に含まれる sample_responseFile ディレクトリを参照してください。
4.3 サイレントインストール実行
この節では、WebLogic Server 14.1.2.0.0 をサイレントモードでインストールする方法を解説します。
事前に準備したレスポンスファイルを指定することで、GUI を使わずに自動的にインストールを行います。
■ インストーラファイルの配置
Oracle 公式サイトから取得したインストーラ(例:fmw_14.1.2.0.0_wls_Disk1_1of1.zip)を展開し、
/u01/software/ 配下に fmw_14.1.2.0.0_wls.jar が存在する状態にしておきます。
■ インストールの実行手順
実行ユーザー: oracle
java -jar /u01/software/fmw_14.1.2.0.0_wls.jar \
-silent \
-responseFile /u01/software/wls_silent.rsp \
-invPtrLoc /etc/oraInst.loc
-silent:サイレントモードで実行-responseFile:作成済みレスポンスファイルのパス-invPtrLoc:Oracle Inventory 情報を格納する/etc/oraInst.locのパス
補足:
-forceオプションは既存ディレクトリを上書きする場合のみ使用してください(通常は不要)。-ignoreSysPrereqsはシステム要件チェックを無視するため、検証環境限定で利用してください。本番では非推奨です。
■ インストールログの確認
処理中に生成されるログを確認し、正常にインストールされたかを確認します。
成功時の例:
Oracle Fusion Middleware 14.1.2 WebLogic Server and Coherence 14.1.2.0.0のインストールが正常に完了しました。
エラーが出た場合はログの末尾を確認し、レスポンスファイルや oraInst.loc の記述に誤りがないかを確認してください。
■ 他の Oracle 製品との共存について
同一ホストに Oracle Database や Oracle Client を導入する場合、これらも同じ oraInventory を共有します。
Inventory の場所やグループ設定が競合しないように注意してください。
5. ドメインの作成(WLST)
5.1 ドメイン作成
Oracle WebLogic Server では、WLST(WebLogic Scripting Tool)を用いてコマンドラインからドメインを作成することができます。
本節では AlmaLinux 9.6 上に構築した WebLogic Server 14.1.2.0.0 環境において、WLST によるドメイン作成スクリプトを準備し実行する手順を紹介します。
■ 実行ユーザー
oracle ユーザーで実行します。
■ スクリプトの目的と構成
本スクリプトは、シンプルな単一構成(AdminServer のみ)を対象に以下の処理を行います。
- テンプレートの読み込み(
readTemplate()) - 管理ユーザー名とパスワードの設定
- 管理サーバー名とポートの指定
- Production モードでのドメイン書き出し(
writeDomain()) - テンプレートのクローズと終了
■ ドメイン作成スクリプト例(create_domain.py)
mkdir -p /u01/oracle/scripts
# create_domain.py
# WebLogicドメイン作成用WLSTスクリプト
cat <<EOF > /u01/oracle/scripts/create_domain.py
readTemplate('/u01/oracle/middleware/wlserver/common/templates/wls/wls.jar')
cd('Security/base_domain/User/weblogic')
cmo.setName('weblogic')
cmo.setPassword('Welcome1')
# 検証用。本番では必ず強固なパスワードに変更すること。この行は実行前に削除してください。SyntaxError: Non-ASCII characterが発生するため。
cd('/')
cd('Server/AdminServer')
cmo.setName('AdminServer')
cmo.setListenPort(7001)
setOption('ServerStartMode', 'prod')
writeDomain('/u01/oracle/domains/base_domain')
closeTemplate()
exit()
EOF
■ 実行方法
/u01/oracle/middleware/oracle_common/common/bin/wlst.sh /u01/oracle/scripts/create_domain.py
■ 注意点
- パスワードは必ず変更してください(推奨:英大小文字・数字・記号を含む 12 文字以上)。
writeDomain()で指定したディレクトリが既に存在するとエラーになります。事前に空であることを確認してください。base_domainという名前は Oracle 標準テンプレートと同じですが、検証環境と本番環境の差異を減らす目的で統一的に使用しています。
■ 参考情報
■ ドメイン作成後の確認ポイント
/u01/oracle/domains/base_domain配下に構成ファイルや起動スクリプトが生成されていることconfig/config.xml内に以下の設定があること:
<production-mode-enabled>true</production-mode-enabled>
startWebLogic.shを実行し、AdminServer がエラーなく起動すること
5.2 管理ユーザーと boot.properties 設定
■ 概要
本節では、Oracle WebLogic Server ドメインに管理ユーザーを設定し、
ドメイン起動時に資格情報を自動で読み込むための boot.properties ファイルを作成する手順を解説します。
この設定により、起動時にユーザー名/パスワードの入力を省略でき、運用自動化や systemd サービス化が容易になります。
■ 前提条件
- 前節(5.2)までに Production モードで
base_domainが作成済みであること - WLST スクリプトで管理ユーザー
weblogicが作成済みであること
■ 1. 管理ユーザーの設定(WLST スクリプトによる作成済み)
WLST スクリプトでは以下のように管理ユーザーが作成されています。
ここでは再確認のために示します。
cd('/Security/base_domain/User/weblogic')
cmo.setPassword('Welcome1') # 検証用。本番では必ず強固な値に変更
■ 2. boot.properties の配置
管理サーバー(AdminServer)のセキュリティディレクトリに boot.properties を作成します。
このファイルには管理ユーザーの認証情報を記述し、WebLogic Server 起動時に自動で読み込まれます。
# 実行ユーザー: oracle
mkdir -p /u01/oracle/domains/base_domain/servers/AdminServer/security
cat <<EOF > /u01/oracle/domains/base_domain/servers/AdminServer/security/boot.properties
username=weblogic
password=Welcome1
EOF
chown oracle:oinstall /u01/oracle/domains/base_domain/servers/AdminServer/security/boot.properties
chmod 600 /u01/oracle/domains/base_domain/servers/AdminServer/security/boot.properties
初回起動時、このファイルは WebLogic により自動的に暗号化され、
平文のパスワードは削除されます。
■ 3. 動作確認
以下のコマンドで管理サーバーを起動し、boot.properties が正しく機能しているかを確認します。
# 実行ユーザー: oracle
cd /u01/oracle/domains/base_domain
./startWebLogic.sh
起動時にユーザー名/パスワードの入力を求められなければ成功です。
起動ログには boot.properties の読み込みに関する記録が残ります。
■ セキュリティ上の注意点
boot.propertiesは初回作成時に平文で保存されるため、chmod 600でアクセス権を制限してください。- 初回起動後は暗号化されるため、セキュリティリスクは大幅に軽減されます。
- 本番環境では、認証情報の管理を運用ポリシーに沿って適切に行ってください。
6. JVM とスレッド設定
6.1 ヒープサイズと GC 設定(1GB 固定)
本節では、WebLogic Server における Java 仮想マシン(JVM)のヒープサイズと GC(ガーベジコレクション)方式の設定について解説します。
本構成では、ヒープサイズを 1GB に固定し、GC は G1GC を利用します。
■ 設定の目的
- ヒープサイズを固定することでメモリ使用量の予測性を高める
- G1GC を使用することで、スループットと応答性のバランスを改善
なお、JDK 21 ではデフォルト GC が G1GC のため、必須ではありません。
ただし運用意図を明示するため、あえて指定することを推奨します。
■ 設定対象ファイル
/u01/oracle/domains/base_domain/bin/setDomainEnv.sh■ 実行ユーザー
oracle ユーザー
■ 設定手順
# バックアップ作成
cp /u01/oracle/domains/base_domain/bin/setDomainEnv.sh \
/u01/oracle/domains/base_domain/bin/setDomainEnv.sh.org
# 編集
vi /u01/oracle/domains/base_domain/bin/setDomainEnv.sh
以下のコメント行を検索します:
# IF USER_MEM_ARGS the environment variable is set, use it to override ALL MEM_ARGS values
この直前または直後に以下を追加してください。
USER_MEM_ARGS="-Xms1024m -Xmx1024m -XX:+UseG1GC"
export USER_MEM_ARGS
これにより、USER_MEM_ARGS が優先され、デフォルトのメモリ設定を上書きできます。
if 文自体を改変する必要はありません。
■ 設定の反映
管理サーバーを再起動すると設定が反映されます。
cd /u01/oracle/domains/base_domain/bin
./stopWebLogic.sh
./startWebLogic.sh
■ 設定確認方法
起動ログまたはプロセス情報から JVM オプションが反映されているか確認します。
ps -ef | grep AdminServer | grep java
出力例:
/usr/java/jdk-21/bin/java -Xms1024m -Xmx1024m -XX:+UseG1GC ... weblogic.Server
■ 補足情報
-Xms:初期ヒープサイズ-Xmx:最大ヒープサイズ-XX:+UseG1GC:G1GC を明示的に有効化(JDK 21 では既定)- チューニング時は GC ログや監視情報を分析し、システム負荷に応じて調整してください。
6.2 スレッド数(最小 = 最大)設定
本節では、WebLogic Server においてスレッド数を固定(最小=最大)に設定する方法を解説します。
スレッド数を固定することで、処理の安定性とリソース使用量の予測性を高めることができます。
WebLogic では WorkManager を通じてスレッド制御を行います。
■ 設定方針
- デフォルト WorkManager(
default)に固定スレッド制約を適用する - 本例では固定スレッド数を 100 に設定(環境に応じて調整可能)
■ スレッド数の決定基準(目安)
Oracle の公式ドキュメントでは具体的な数式は提示されていません。
実務上の初期目安として、論理 CPU コア数 × 2〜4 がよく用いられます。
| 論理コア数 | 推奨スレッド数(目安) | 用途例 |
|---|---|---|
| 2 | 4~8 | 軽量なテスト環境 |
| 4 | 8~16 | 一般的な開発環境 |
| 8 | 16~32 | 中規模~本番環境 |
| 16 | 32~64 | 高負荷・並列性重視 |
ただし最適値はアプリケーション特性に依存するため、負荷試験に基づいた調整が推奨されます。
■ 設定スクリプト(WLST)
実行ユーザー: oracle
※実行時は日本語箇所、全角箇所は削除してください。
存在するとエラーになります。
# set_threads.py
# WorkManager のスレッド数固定設定用 WLST スクリプト
cat <<EOF > /u01/oracle/scripts/set_threads.py
connect('weblogic', 'Welcome1', 't3://localhost:7001')
edit()
startEdit()
# MyWorkManager を作成して適用
cd('/SelfTuning/base_domain')
wm = cmo.createWorkManager('MyWorkManager')
wm.addTarget(getMBean('/Servers/AdminServer'))
# MinThreadsConstraint の作成
cd('/SelfTuning/base_domain')
mtc = getMBean('/SelfTuning/base_domain/MinThreadsConstraints/FixedThreadsMin')
if mtc is None:
# 存在しなければ新規作成
mtc = cmo.createMinThreadsConstraint('FixedThreadsMin')
mtc.setCount(100)
print('MinThreadsConstraint "FixedThreadsMin" is created')
else:
# 存在すれば編集
cd('/SelfTuning/base_domain/MinThreadsConstraints/FixedThreadsMin')
mtc.setCount(100)
print('Edited existing "FixedThreadsMin"')
# MaxThreadsConstraint の作成
cd('/SelfTuning/base_domain')
mtc = getMBean('/SelfTuning/base_domain/MaxThreadsConstraints/FixedThreadsMax')
if mtc is None:
# 存在しなければ新規作成
mtc = cmo.createMaxThreadsConstraint('FixedThreadsMax')
mtc.setCount(100)
print('MaxThreadsConstraint "FixedThreadsMax" is created')
else:
# 存在すれば編集
cd('/SelfTuning/base_domain/MaxThreadsConstraints/FixedThreadsMax')
mtc.setCount(100)
print('Edited existing "FixedThreadsMax"')
cd('/SelfTuning/base_domain/WorkManagers/MyWorkManager')
cmo.setMinThreadsConstraint(getMBean('/SelfTuning/base_domain/MinThreadsConstraints/FixedThreadsMin'))
cmo.setMaxThreadsConstraint(getMBean('/SelfTuning/base_domain/MaxThreadsConstraints/FixedThreadsMax'))
save()
activate()
disconnect()
exit()
EOF
■ スクリプトの実行
/u01/oracle/middleware/oracle_common/common/bin/wlst.sh /u01/oracle/scripts/set_threads.py
■ 設定確認方法(WLST)
/u01/oracle/middleware/oracle_common/common/bin/wlst.sh
connect('weblogic', 'Welcome1', 't3://localhost:7001')
cd('/SelfTuning/base_domain/WorkManagers/MyWorkManager')
print('MinThreadsConstraint=' + str(cmo.getMinThreadsConstraint().getCount()))
print('MaxThreadsConstraint=' + str(cmo.getMaxThreadsConstraint().getCount()))
disconnect()
exit()
■ Remote Console での確認方法
- WebLogic Remote Console にログイン
- 左側メニューから Self Tuning → Work Managers を選択
MyWorkManagerを選択- [Constraints] タブで Min/MaxThreadsConstraint が
FixedThreadsMin/FixedThreadsMaxになっていることを確認
7. JDBC データソース作成(WLST)
7.1 データソース作成スクリプトの準備と実行
この節では、WLST(WebLogic Scripting Tool)を用いて JDBC データソースを作成するためのスクリプトを準備し実行します。
接続先データベースは、以下の記事で構築した Oracle Database 23ai Free を使用します。
▶ Oracle Database 23ai Free の構築手順(参考)
■ 作成対象の JDBC データソース概要
- データソース名:
MyDS - JNDI 名:
jdbc/MyDS - ドライバ:Oracle JDBC Thin Driver(WebLogic 同梱ドライバ利用)
- 接続先:
jdbc:oracle:thin:@//db.localdomain:1521/FREEPDB1 - DB ユーザー:
wls_user - DB パスワード:
Welcome1(検証用。本番では必ず変更) - ターゲットサーバー:
AdminServer
■ WLST スクリプト例
※実行時は日本語箇所、全角箇所は削除してください。
存在するとエラーになります。
# create_datasource.py
# JDBC データソース作成用 WLST スクリプト
cat <<EOF > /u01/oracle/scripts/create_datasource.py
from java.lang import String
import jarray
from javax.management import ObjectName
connect('weblogic', 'Welcome1', 't3://localhost:7001')
edit()
startEdit()
# データソース作成
cd('/')
cmo.createJDBCSystemResource('MyDS')
cd('/JDBCSystemResources/MyDS/JDBCResource/MyDS')
cmo.setName('MyDS')
# JNDI 名設定
cd('/JDBCSystemResources/MyDS/JDBCResource/MyDS/JDBCDataSourceParams/MyDS')
set('JNDINames', jarray.array(['jdbc/MyDS'], String))
# 接続設定
cd('/JDBCSystemResources/MyDS/JDBCResource/MyDS/JDBCDriverParams/MyDS')
cmo.setUrl('jdbc:oracle:thin:@//db.localdomain:1521/FREEPDB1')
cmo.setDriverName('oracle.jdbc.OracleDriver')
cmo.setPassword('Welcome1')
# パスワードはDB接続のパスワードを設定。
# 接続で使用する DB ユーザー指定
cd('/JDBCSystemResources/MyDS/JDBCResource/MyDS/JDBCDriverParams/MyDS/Properties/MyDS')
cmo.createProperty('user')
cd('/JDBCSystemResources/MyDS/JDBCResource/MyDS/JDBCDriverParams/MyDS/Properties/MyDS/Properties/user')
cmo.setValue('wls_user')
# テスト用SQL設定
cd('/JDBCSystemResources/MyDS/JDBCResource/MyDS/JDBCConnectionPoolParams/MyDS')
cmo.setTestTableName('SQL SELECT 1 FROM DUAL')
cmo.setInitialCapacity(100)
cmo.setMaxCapacity(100)
# ターゲット設定
cd('/JDBCSystemResources/MyDS')
cmo.addTarget(getMBean('/Servers/AdminServer'))
save()
activate()
disconnect()
exit()
EOF
■ 実行方法
/u01/oracle/middleware/oracle_common/common/bin/wlst.sh /u01/oracle/scripts/create_datasource.py
■ 実行結果確認
WLST 実行後、以下のように表示されれば成功です。
アクティブ化が完了しました
WebLogic Remote Console を使用する場合は、Services → Data Sources に MyDS が表示されることを確認してください。
■ 補足:Multi Data Source / GridLink の活用
- Multi Data Source: 複数のデータソースを束ねてフェイルオーバーやロードバランシングを実現
- GridLink Data Source: Oracle RAC と連携し、FAN(Fast Application Notification)や ONS に対応した高可用構成
本記事では単一データソースを前提としていますが、本番環境で高可用性が求められる場合にはこれらの構成を検討してください。
■ 設定確認方法
WLST コンソールで以下を実行し、設定内容を確認します。
/u01/oracle/middleware/oracle_common/common/bin/wlst.sh
connect('weblogic', 'Welcome1', 't3://localhost:7001')
cd('/JDBCSystemResources/MyDS/JDBCResource/MyDS/JDBCDriverParams/MyDS')
print(cmo.getUrl())
cd('Properties/MyDS/Properties/user')
print(cmo.getValue())
disconnect()
exit()
■ セキュリティ上の注意点
- スクリプトにパスワードを平文で記述するのは非推奨です。
- 本番環境では Credential Store を利用するか、外部プロパティファイルから読み込む方法を検討してください。
- 少なくとも検証環境でも
chmod 600などでスクリプトの権限を制限してください。
7.2 DataBase への接続テスト
前節で作成・設定した JDBC データソース MyDS を使い、データベースへの接続確認を行います。
本節では、WLST を用いた操作手順と、WebLogic Remote Console を利用した確認方法を紹介します。
■ 接続テストの実行
AdminServer のランタイム MBean に移動し、接続テストを実施します。
/u01/oracle/middleware/oracle_common/common/bin/wlst.sh
connect('weblogic', 'Welcome1', 't3://localhost:7001')
domainRuntime()
cd('/ServerRuntimes/AdminServer/JDBCServiceRuntime/AdminServer/JDBCDataSourceRuntimeMBeans/MyDS')
testResult = cmo.testPool()
if testResult is None:
print("Success: Connection test passed.")
else:
print("Failed: " + str(testResult))
戻り値が Success であれば接続は正常です。
■ 補足
- 接続テストには AdminServer へのターゲット設定が必須です。
- Oracle JDBC ドライバは WebLogic に同梱されているため追加導入は不要です。
- 本番環境では WLST スクリプトに認証情報を平文で記載せず、Credential Store などを利用してください。
8. WebLogic Remote Console の利用
8.1 Remote Console の入手方法
WebLogic Remote Console(WRC)は、Oracle WebLogic Server ドメインを管理するためのスタンドアロン型の GUI ツールです。従来の /console に代わる公式ツールとして提供されており、特に Linux サーバーに WebLogic を構築し、Windows 11 PC からリモート管理する用途に適しています。
■ 利用構成
本記事では、WRC を Windows 11 PC 上で実行し、Linux 上の WebLogic Server(AdminServer)に接続する構成を前提とします。
■ 入手方法
WebLogic Remote Console は Oracle の公式 GitHub リポジトリから入手可能です。
常に最新版を利用するため、以下のリリースページからダウンロードしてください。
▶ WebLogic Remote Console – GitHub Releases
■ ダウンロードと展開(Windows 11)
- リリースページから
weblogic-remote-console-*-windows-x64.zipをダウンロードします。 - 任意のフォルダ(例:
C:\WRC)に ZIP ファイルを展開します。 - 展開先に含まれる
weblogic-remote-console.exeをダブルクリックして起動します。
■ 初回起動時の挙動
起動すると自動的にブラウザが開き、以下の URL にアクセスします。
http://APサーバーのIPアドレス:7001この画面から WebLogic ドメインに接続して管理作業を行えます。
■ 通信要件
- WRC は WebLogic Server に対して REST API を使用して接続します。
- AdminServer 側のポート(通常 7001)が Windows PC から到達可能である必要があります。
- 必要に応じて Linux 側の firewall や SELinux 設定を調整してください。
■ セキュリティ注意事項
- 管理対象が外部公開サーバーの場合、必ず SSL/TLS(HTTPS)を利用してください。
- WRC 側には認証情報が保存されるため、利用後は不要な接続情報を削除することを推奨します。
8.2 AdminServer への接続方法
この節では、Windows 11 上で実行している WebLogic Remote Console(WRC)を用いて、
Linux 上で稼働する WebLogic Server の AdminServer に接続する方法を解説します。
■ 前提条件
- AdminServer が Linux 上で起動済みであること
- AdminServer のポート
7001に Windows PC からアクセス可能であること(Firewall/SELinux 設定済み) - Windows 11 PC にて WRC を展開済みであること
■ WRC の起動
- Windows エクスプローラで、展開したフォルダ(例:
C:\WRC)に移動します。 weblogic-remote-console.exeをダブルクリックして起動します。
■ AdminServer への接続手順
- [Connect to an Administration Server] をクリック
- 以下の情報を入力します:
- Administration Server URL:
http://<APサーバーのIP>:7001 - Username:
weblogic - Password:
Welcome1(検証用。本番は必ず変更) - セキュアでない接続の確立:チェックを入れる
入力後、[Connect] をクリックします。
■ 接続成功時の確認
- 左ペインに「Domain」ツリーが表示される
- [Environment] → [Servers] から AdminServer の状態が確認できる
- [Services] → [Data Sources] から JDBC 設定が確認できる
■ トラブルシューティング
- 接続できない場合: AdminServer が起動しているか、Linux 側で 7001 番ポートが解放されているか確認
- 認証エラー: ユーザー名・パスワードが正しいか、
boot.propertiesと整合性があるか確認
■ セキュリティ上の注意
- 外部公開環境では、必ず HTTPS を利用してください。
- 認証情報は本番環境用に強固なパスワードを設定し、定期的に更新してください。
8.3 ドメイン管理とリソース確認
WebLogic Remote Console(WRC)は、従来のブラウザベース管理コンソール(/console)に代わる最新の管理ツールです。
ここでは WRC を利用して、ドメインの構成状態や各種リソースを確認する方法を解説します。
■ 実行環境
Windows 11 PC 上で WRC を実行し、Linux 上の AdminServer に接続します。
■ 操作手順
- 展開済みの
weblogic-remote-console.exeをダブルクリックして起動します。 - ブラウザが開き、
http://APサーバーのIPアドレス:7001にアクセスされます。 - 「Enter WebLogic Remote Console」をクリックします。
- 接続済みのドメイン(例:
base_domain)を選択します。
■ 確認できる主なリソース
- Domain: ドメイン名、Production モード設定など全体の構成情報
- Environment → Servers: AdminServer の状態、ポート番号、ログ出力設定
- Services → Data Sources: JDBC データソースの一覧、JNDI 名、接続 URL、テスト結果
- Security → Realms: デフォルトセキュリティレルム(myrealm)とユーザー管理設定
■ JDBC データソースの接続確認
- 左ペインで Services → Data Sources を選択
- 確認対象のデータソース(例:
MyDS)をクリック - [一般] タブを開き、「構成のテスト」をクリックして実行
- 成功すれば
WebLogicドメインの管理サーバーからこのデータ・ソースのデータベースに正常に接続しました。と表示されます
■ 注意事項
- WRC はクライアントツールであり、WebLogic サーバー側への追加インストールは不要です。
- REST API 経由で通信するため、外部公開環境では必ず HTTPS を利用してください。
- ユーザー・セキュリティ設定の変更は影響が大きいため、検証環境で十分に確認した上で本番に反映してください。
- 一部の詳細設定は WLST でのみ可能なため、WRC と WLST を併用することを推奨します。
9. 運用準備
9.1 systemd による自動起動設定
WebLogic Server の運用では、OS 起動と同時に管理サーバー(AdminServer)が自動的に起動・停止するようにすることが重要です。
ここでは systemd を用いて WebLogic をサービス化し、自動起動を設定します。
■ 前提条件
- ドメイン
/u01/oracle/domains/base_domainが作成済みであること boot.propertiesが設定され、自動ログイン可能であること- OS:AlmaLinux 9.6
- WebLogic バージョン:14.1.2.0.0
- 実行ユーザー:
oracle(oinstallグループ所属)
■ systemd ユニットファイルの作成
作業ユーザー: root
vi /etc/systemd/system/wls-admin.service
以下の内容を記述してください:
[Unit]
Description=Oracle WebLogic AdminServer
After=network.target
[Service]
Type=simple
User=oracle
Environment=DOMAIN_HOME=/u01/oracle/domains/base_domain
ExecStart=/bin/bash -c "$$DOMAIN_HOME/bin/startWebLogic.sh >> $$DOMAIN_HOME/servers/AdminServer/logs/startup.out 2>&1"
ExecStop=/bin/bash -c "$$DOMAIN_HOME/bin/stopWebLogic.sh >> $$DOMAIN_HOME/servers/AdminServer/logs/shutdown.out 2>&1"
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
■ サービスの有効化と起動
systemctl daemon-reload
systemctl enable wls-admin.service
systemctl start wls-admin.service
■ サービス状態の確認
systemctl status wls-admin.service
active (running) と表示されていれば正常に起動しています。
■ サービスの停止確認
systemctl stop wls-admin.service
systemctl status wls-admin.service
inactive (dead) と表示され、shutdown.out に停止ログが記録されていれば成功です。
■ OS 再起動後の動作確認
reboot
再起動後に以下を実行し、AdminServer が自動起動していることを確認してください。
systemctl status wls-admin.service
■ 注意事項
boot.propertiesを未設定の場合、自動起動時に認証エラーとなります。- ログファイルは以下に出力されます:
/u01/oracle/domains/base_domain/servers/AdminServer/logs/startup.out
/u01/oracle/domains/base_domain/servers/AdminServer/logs/shutdown.out - systemd は標準で journald にログを記録するため、リダイレクトを省略し journald で統合管理する方法も選択可能です。
- 停止処理には時間がかかる場合があるため、
TimeoutStopSec=600を設定しています。 - 複数サーバー構成の場合、Managed Server 用に別途 systemd サービスを定義してください(例:
wls-ms1.service)。 - 本番環境では
oracle汎用ユーザーではなく、専用の WebLogic サービスユーザーを作成して権限分離することが推奨されます。
9.2 ログ出力・ローテーションの設定
Oracle WebLogic Server には標準でログ出力・ローテーション機能が備わっており、サーバーやドメインの稼働状況を把握する上で重要です。
適切に設定しないとログが肥大化し、ディスク圧迫や調査性の低下につながるため、本節ではログ出力先の整理とローテーション設定を解説します。
■ 主なログの種類
- Server Log: 各サーバー(AdminServer, ManagedServer)の稼働状況を記録(例:
server.log) - Domain Log: ドメイン全体のイベントを集約(任意で利用可能)
- HTTP Access Log: HTTP リクエスト単位のアクセス記録(任意で有効化)
- セキュリティログ: 認証・監査情報(Security Realm 設定に依存)
■ ログ出力先(例)
/u01/oracle/domains/base_domain/servers/AdminServer/logs/server.log
/u01/oracle/logs/access/access.log
■ WLST によるログローテーション設定
実行ユーザー: oracle
/u01/oracle/middleware/oracle_common/common/bin/wlst.sh
connect('weblogic', 'Welcome1', 't3://localhost:7001')
edit()
startEdit()
# AdminServer のログ設定
cd('/Servers/AdminServer/Log/AdminServer')
cmo.setRotationType('bySize') # サイズベース
cmo.setFileMinSize(500) # 500KB でローテーション
cmo.setFileCount(10) # 最大10世代保持
cmo.setRotateLogOnStartup(True) # 起動時にローテーション
save()
activate()
disconnect()
exit()
ローテーション方式には bySize(サイズ基準)と byTime(時間基準)があり、環境に応じて選択可能です。
■ HTTP Access Log の設定(任意)
connect('weblogic', 'Welcome1', 't3://localhost:7001')
edit()
startEdit()
cd('/Servers/AdminServer/WebServer/AdminServer/WebServerLog/AdminServer')
cmo.setLoggingEnabled(True)
cmo.setLogFileFormat('common') # 'extended' も選択可能
cmo.setFileName('/u01/oracle/logs/access/access.log')
cmo.setRotationType('bySize')
cmo.setFileMinSize(1000) # 1MB ごとにローテーション
cmo.setFileCount(30) # 最大30世代保持
cmo.setRotateLogOnStartup(True)
save()
activate()
disconnect()
exit()
■ ログファイル例(ローテーション後)
server.log
server.log00001
server.log00002
...
■ 運用上の注意事項
- ローテーションを設定しないとログが無制限に肥大化するため、必ず設定してください。
- 重要なログはアーカイブ・転送などで定期的にバックアップしてください。
- OS 標準の
logrotateと組み合わせることで、ファイル圧縮や長期保管ポリシーを柔軟に実現できます。 - アクセスログには機微情報が含まれる可能性があるため、アクセス権限管理を徹底してください。
- 本番環境では監査要件に基づき、セキュリティログや監査ログを別途保存する運用も推奨されます。
9.3 バックアップとパッチ適用準備
本節では、WebLogic Server の構築完了後に取得すべき初期バックアップと、将来的なパッチ適用に備えた準備手順について解説します。
■ バックアップの取得
WebLogic Server の構成情報やスクリプト類は復旧の要となるため、構築直後に必ずバックアップを取得してください。
実行ユーザー: oracle
cd /u01/oracle
tar czvf backup_initial_config_$(date +%Y%m%d).tar.gz \
domains/base_domain \
middleware/wlserver/common/bin/wlst.sh \
scripts \
/u01/software/wls_silent.rsp \
oraInventory
domains/base_domain:ドメイン構成(config.xml など)scripts:WLST や管理用シェルスクリプト/u01/software/wls_silent.rsp:サイレントインストール時のレスポンスファイルoraInventory:Oracle 製品のインストール情報middleware:WebLogic 本体(再インストールを省略したい場合)
取得したバックアップは 外部ストレージやセキュアなリポジトリ に安全に保管し、アクセス権限を制限してください。
■ パッチ適用準備
WebLogic Server では、セキュリティ修正やバグ修正のために定期的にパッチ(CPU: Critical Patch Update)が提供されます。
適用には OPatch ユーティリティを使用します。
1. OPatch バージョン確認
実行ユーザー: oracle
export ORACLE_HOME=/u01/oracle/middleware
export PATH=$ORACLE_HOME/OPatch:$PATH
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch version
出力例:
OPatch Version: 13.9.4.2.9
バージョンが古い場合は My Oracle Support より最新版を取得してください。
2. パッチファイルの入手と展開
mkdir -p /u01/oracle/patches
unzip p34567890_141200_Linux-x86-64.zip -d /u01/oracle/patches/
※ パッチ番号(例:p34567890_141200_Linux-x86-64.zip)は WebLogic のバージョンと OS に依存します。
3. パッチ前提条件の確認
パッチ適用前に、展開先ディレクトリの README.txt を必ず確認してください。
前提条件や競合パッチの有無、再起動の必要性などが記載されています。