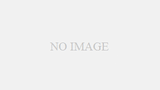第07回
ChatGPTの出力に対して評価や改善を依頼する方法
- 目的:出力に対して評価や改善提案を依頼する技法を学ぶ
- ゴール:出力をブラッシュアップする会話ができるようになる
- 読者ターゲット:ChatGPTをある程度使っているが、「回答がいまいちピンとこない」と感じる人。特に、より良い答えを引き出す方法を知りたい初心者〜中級者におすすめ。
7-1. なぜフィードバックが必要なのか?
7-1-1. ありがちな失敗パターン ❌
以下のような依頼では、ChatGPTの改善力をうまく引き出せません。
- 「もっと良くして」だけの曖昧な依頼
- 評価や改善の基準が指定されていない
- どの点を直してほしいかを伝えていない
7-1-2. 評価を依頼するプロンプト 📌
ChatGPTは、自分の出力に対して自動的に反省したり改善したりはしません。
ですが「評価して」と依頼すれば、指定した基準に沿って内容を見直すモードに入ります。
たとえば「わかりやすさ」や「構成の論理性」などの評価基準を与えることで、
ChatGPTはその観点で“自己レビュー”を行い、次の改善につなげやすくなります。
ChatGPTに「この回答を5段階で評価して」「わかりやすさをチェックして」と頼むと、
自己点検モードに入り、建設的なフィードバックが得られます。
自己点検モードに入り、建設的なフィードバックが得られます。
7-1-3. ChatGPTの評価傾向を知っておこう 🧠
- 基本的に「やや甘め」の点数評価になりがち(平均4点以上)
- 改善点は1〜2つの浅い指摘で終わることもある
- 「理由」と「改善案」も必ず求めるのがポイント
7-2. 効果的な改善依頼の出し方
7-2-1. 目的別・改善依頼テンプレート集 📘
- 【読みやすさ改善】「もっと短く、リズムよく書き直して」
- 【説得力向上】「論理展開が弱い部分を補強して」
- 【トーン調整】「カジュアルで親しみやすい文体にして」
- 【要約・圧縮】「この内容を200文字以内にまとめて」
7-2-2. 出力タイプ別・改善のコツ 📂
| 出力タイプ | 出力結果 | 改善プロンプト例 |
|---|---|---|
| 要約文 | 長すぎ・抽象的になりがち | 「具体的な例を交えて要約して」 |
| 説明文 | 専門用語が多く読みにくい | 「初心者でも理解できるように書き直して」 |
| 企画提案 | 納得感や根拠が弱い | 「このアイデアに説得力を持たせる補足を加えて」 |
7-2-3. 自動フィードバックテンプレートを作ろう ✅
この回答を以下の観点でレビューしてください。
1. わかりやすさ(5点満点)とその理由
2. 論理構成の良し悪し
3. 改善すべきポイントとその理由
4. 改善案の提案7-3. ステップで実践する:改善の流れを体験
7-3-1. 段階的な改善ステップ 📊
改善の基本は「評価 → 改善点の抽出 → 修正出力 → 比較と調整」です。
| ステップ | やること | プロンプト例 |
|---|---|---|
| 1. 評価依頼 | 点数と理由で振り返らせる | 「この回答を5点満点で評価し、理由も教えて」 |
| 2. 改善点抽出 | どこを直せば良いか考えさせる | 「改善できそうな点を3つ教えて」 |
| 3. 改善版作成 | 指摘をもとに再出力 | 「それをふまえて改善バージョンを作って」 |
| 4. 比較と再調整 | Before/Afterで違いを確認 | 「元と改善後を比較して表にまとめて」 |
7-3-2. ステップ実例:会話形式で流れを確認 💬
【あなた】
この文章を評価して、わかりやすさと改善点を教えて。
「AIは人工知能の略であり、機械が人間のように学習し判断することを意味します。」
【ChatGPT】
評価:3.5点
理由:意味は正しいが少し硬く、具体例がない
改善点:
- 「人工知能」の定義が抽象的
- 文が長く、リズムが悪い
- 子どもには難しい語句がある
【あなた】
では、わかりやすく改善したバージョンを出して。
【ChatGPT】
「AI(人工知能)は、人のように考えたり学んだりするコンピュータです。たとえば、質問に答えたり、会話したりできます。」
【あなた】
元の文と比較して、違いを表にまとめて。
【ChatGPT】
| 項目 | 元の文 | 改善後 |
|------|--------|--------|
| 難易度 | 難しい表現 | 子どもでも理解できる |
| 長さ | 一文が長い | 文を短く分けた |
| 例 | 抽象的 | 会話例を追加 |
7-4. 応用編:よりよい出力に磨き上げる
7-4-1. 実務でのフィードバック活用シーン 💼
| シーン | 活用例 | 改善依頼プロンプト例 |
|---|---|---|
| メール文面 | トーンが硬すぎるかチェック | 「このメール、もう少し柔らかくできますか?」 |
| 社内資料 | 論理構成が伝わるか確認 | 「この説明、わかりやすさを5点で評価して」 |
| プレゼン原稿 | 聞き手視点で改善 | 「中学生にも伝わるように修正して」 |
7-4-2. 微調整するときのひと工夫 🎯
- 部分的な表現を指定:「2文目が長い気がします」
- 印象の調整:「もう少しフレンドリーに」
- 1つだけ直す:「重要語句の順番だけ工夫して」
7-4-3. やってはいけない改善依頼の例 ⚠️
- 「いい感じにして」→ 抽象的すぎて伝わらない
- 「直して。でも元の雰囲気はそのまま」→ 矛盾した指示
- 「改善案だけ出して」→ 評価・改善理由が得られない
7-4-4. 活用イメージ:こんな場面で役立ちます 📣
あるライターが、ChatGPTで原稿の下書きを作ったところ「それっぽいけど伝わらない…」という状態に。
そこで、出力に対して「わかりやすさを5点で評価して」「改善点を3つ挙げて」と依頼。
結果、具体例と語尾の調整が入り、読み手視点に寄り添った文章に進化しました。
そこで、出力に対して「わかりやすさを5点で評価して」「改善点を3つ挙げて」と依頼。
結果、具体例と語尾の調整が入り、読み手視点に寄り添った文章に進化しました。
7-5. 比較と次のステップへ
7-5-1. プロンプト+ChatGPT回答の実例 ✅
【プロンプト】
以下の説明文を中学生にも伝わるよう改善し、改善点を表でまとめてください。
「AIは人工知能の略であり、機械が人間のように学習し判断することを意味します。」
【改善後】
「AIとは、人のように学んだり考えたりできるコンピュータです。たとえば、質問に答えたり、会話したりします。」
【比較表】
| 項目 | 元の文 | 改善後 |
|------|--------|--------|
| 用語 | 専門的 | やさしい言葉に変更 |
| 構文 | 抽象的で長文 | 短文+具体例あり |
| トーン | 硬め | なめらか・親しみやすい |
7-5-2. まとめ:フィードバックは対話の入口 📎
- 出力への「評価依頼」で弱点を発見
- 「改善提案」で構成やトーンを修正
- 「改善版と比較」で納得度を高める
- ChatGPTの“癖”を知り、自分の意図を伝える精度を磨こう
🔐 注意:ChatGPTの評価は万能ではありません。
最終判断には、あなた自身の視点や目的を必ず反映させましょう。
最終判断には、あなた自身の視点や目的を必ず反映させましょう。
7-5-3. 次回予告:さらに精度を高める“会話力”へ 🪄
今回の記事では、ChatGPTの出力に対して評価や改善を依頼する方法を学びました。
このスキルを身につけたあなたは、次に「会話の中で精度を上げる」ステージへ進めます。
次回(第8回)は、追加質問や再指示によって、回答の質を高めるテクニックを解説します。
「もう少し詳しく」「表にして」「別の視点から」など、会話の中で微調整する力が身につきます。
📘 ChatGPTとの対話は、1往復では終わりません。
次回は「2往復・3往復」でより良い答えを引き出すコツをお届けします。
次回は「2往復・3往復」でより良い答えを引き出すコツをお届けします。